2024年4月23日花は匂えど散りぬるを
 ソメイヨシノの花が散り、新緑が一段と美しい4月半ばに、
ソメイヨシノの花が散り、新緑が一段と美しい4月半ばに、
八重の桜が、次々咲きました。 かつて、新宿御苑には、
素晴らしい八重桜が、それはそれは沢山あったのですが、
枝の枯損や衰弱で、ずいぶん伐採され、減ってしまいました。
今年心に沁みたのは、「福禄寿」です。
これは荒川堤に由来する栽培品種の一つだそうです。
咲きつつあり、散りつつある、そんな姿をみせてくれた2週間。
さようなら、また来年も咲いてください。
 ソメイヨシノの花が散り、新緑が一段と美しい4月半ばに、
ソメイヨシノの花が散り、新緑が一段と美しい4月半ばに、
八重の桜が、次々咲きました。 かつて、新宿御苑には、
素晴らしい八重桜が、それはそれは沢山あったのですが、
枝の枯損や衰弱で、ずいぶん伐採され、減ってしまいました。
今年心に沁みたのは、「福禄寿」です。
これは荒川堤に由来する栽培品種の一つだそうです。
咲きつつあり、散りつつある、そんな姿をみせてくれた2週間。
さようなら、また来年も咲いてください。
 今朝、細かい霧雨の中、うっすらと虹が架かった。
今朝、細かい霧雨の中、うっすらと虹が架かった。
見えますか。 蜘蛛の糸のようです。
 小石川植物園で、満開の桜を見上げていたが、
小石川植物園で、満開の桜を見上げていたが、
その賑わいから少し離れた森陰にも、可憐な花が咲いていた。
オオアマナ、地上に落ちた星のように、足元に咲く小さな花だ。
あぁ、しかし、この花の球根にも、毒があるらしい。
毒のある植物は、薬として用いられる可能性がある。
小石川植物園は、小石川養生所だったから、薬草も豊富なはず。
世界は謎に満ちていて、植物の毒性も薬の可能性に満ちている。
また逆に、薬だと思っていたら毒だった、と言うこともあるだろう。
何も知らずに生きている、そんな気がする春である。
 2024年3月11日、陶芸作家リサ・ラーソンが他界された。享年92歳。
2024年3月11日、陶芸作家リサ・ラーソンが他界された。享年92歳。
日本でも大人気の作家さんで、最後までその人気は衰えなかった。
このエッグスタンドも、リサ・ラーソンのデザインで、1980年代に生産された、
せっ器である。 個体差があり、一つ一つ風合いが異なる。
丸ごと食べてしまいたいくらい、味のある手触りだ。
今年2024年の復活祭は3月31日、復活祭といえば、卵、イースターエッグである。
森の中にある格調高いホテルで、朝食に、ゆで卵を頼んでしまったことがある。
なぜかナイフとフォークが添えられており、悩みが深まった。
ゆで卵って、ナイフとフォークで食べるものだったのでしょうか?
 神社の境内で、朝のラジオ体操の最中でした。
神社の境内で、朝のラジオ体操の最中でした。
木の枝にとまっていた鳩が、突然、眼前の地面に落下しました。
地べたでバサバサ羽ばたいて回転したと思ったら、仰向けになり、
そのまま事切れてしまったのです。
ラジオ体操を終えて、人々が鳩の廻りに集まってきて、
「突然死ですね」「おそらく心筋梗塞でしょうな」
様々な声が寄せられました。「でも、触らない方がいいでしょう」
一体何が起こったのか。 ふっくらとした美しい鳩でした。
この写真は、夫が記録として撮影したものです。
「これは幸福な死ですよ」そう言ったのは、高齢のおじいさんでした。
 我が家には、以前から、「茂吉」というオオカミ犬がいる。
我が家には、以前から、「茂吉」というオオカミ犬がいる。
そこへ一昨年、「伸介」という柴犬小僧が加わった。
茂吉は、野性的な風貌が魅力的だが、
伸介は、その手のぶらぶら感がいい。ただ、
犬だという自覚がやや希薄であるような気がする。
いずれも、自力では動けない。 ぬいぐるみだからだ。
しかし、その役割は重要で、茂吉は寝室の窓際で、
伸介は仕事部屋の入り口で、それぞれ番をしている。
春には、独特の寂しさがある。
想像力の中で、伸介が「とうせんぼう」をしている。なぜかしら?
 今年最初のアネモネが、ベランダで開花しました。
今年最初のアネモネが、ベランダで開花しました。
「め・ざ・め・ました」というように。
つぶらな瞳のようなのです。
でも、本当にこれが目だったら、
それはそれで、こわいような気がします。
花粉の季節ですね。
「リトル・ジョー」という植物映画を思い出します。
花粉・ウイルス・感染によって置き換えられる脳内物質?・・・
振り返ってみると、予言的想像力の世界でした。
 ポインセチアの異変に気づきました。
ポインセチアの異変に気づきました。
花の中から、ニョッキリ、ポッテリ、何かが伸びているではありませんか。
これまでの人生で初めて見る光景です。
このポインセチアは、去年の暮れ、近所の花屋さんで買いました。一鉢千円。
いつも良い花を仕入れてくれる花屋さんで、町の彩りでしたが、
年が明けて、その店の前を通ると、閉店のお知らせが貼ってあリました。
その店で最後に買ったポインセチアに、初めましての実がなったのです。
ひとつの扉が閉まるとき、別の扉が開かれるように。
「希望はあるよ」と告げている。
 13年前の開花は夏だったので、屋外に展示されました。
13年前の開花は夏だったので、屋外に展示されました。
開花の翌日から徐々にしぼみ始め、もう匂いもありませんでした。 2010年夏の思い出。
 小石川植物園のショクダイオオコンニャクは、2023年12月8日朝、
小石川植物園のショクダイオオコンニャクは、2023年12月8日朝、
13年ぶりの開花が確認され、数日後には崩れ、根本から切断(写真)、
今は標本となっているそうです。
13年前は夏の開花でしたが、温室で過ごしており、本人のタイミングで咲くため、
今回は冬の開花となってしまいました。
「呼び寄せるはずの昆虫もハエ一匹おらず、本人としては、無念であったろう」と
植物園関係者が話されていました。
思いがけない幸運もあれば、思いがけない不運もある。
それでも咲いてくれたこと、立派でしたよ、冬の花。
 小石川植物園の温室で、
小石川植物園の温室で、
ショクダイオオコンニャクが、13年ぶりに開花しそうです。
写真は、12月2日、巨大なつぼみの状態です。
開花まで秒読みです。
開花すると数時間はものすごく臭く、その匂いで虫を寄せ付けます。
ほんの数日で花はしおれてしまうため、来園者も押し寄せます。
13年前は、倒れる人が出たほどです。
気をつけましょう。
*
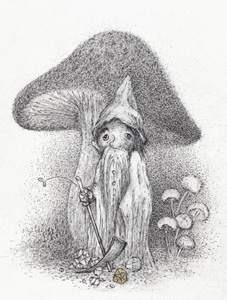 トルコの珈琲占いは、濃厚なトルコ式コーヒーを飲み終えたその人のカップを
トルコの珈琲占いは、濃厚なトルコ式コーヒーを飲み終えたその人のカップを
伏せて暫く置き、カップの内側に残ったコーヒーかすの模様を読み解く。
それで、「あなたの家は、天使に守られている」と告げられたことがある。
占いなんて信じない。だけど、天使はいるかもしれない、と思った。
ただ、その天使、金髪巻き毛のかわい子ちゃんとはかぎらない。
みすぼらしい老人の姿をしているかもしれないのである。
グノムという精霊は、土から石を掘り出す「契約」の天使(老人)であり、
それを裏切ると大変なことになる、とても恐いコビトだという話がある。
童話「白雪姫」に出てくる「7人のコビト」の原型も、グノムであろう。
この話しについても、特に信じる根拠はない。
 秋は、貪欲になります。そして、忙しい。
秋は、貪欲になります。そして、忙しい。
実りの秋、紅葉狩りの秋、芸術の秋、食欲の秋・・・
気候が変わるように、気分も変えたくなる。
陶芸家キムホノさんの新しいうつわを発掘してきました。
柏のギャラリー「うつわ萬器」で。<キムホノ展>12日まで開催中。
同じ器はひとつもない。それぞれの手ざわり。 おもしろい。
自由な発想、楽しい食卓、感謝の秋である。
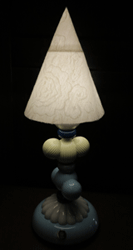 秋めいてきた。
秋めいてきた。
多和田葉子さんの小説「白鶴亮翅」の中に、興味深い幽霊話が出てくる。
主人公が通っている太極拳教室の友達の様子がおかしい。げっそりやつれている。どうしたのか。
夜入浴のために湯をはると、バスタブの中に女性の死体(幽霊)が横たわっているのだという。
その問題を解決するために、一人暮らしの彼女の住まいを訪ね、
心霊儀式のように、お茶を飲みながら夜話しをする。そして、バスタブに向かってみると・・・
母娘の心理と蜘蛛の巣が絡み合って見えてくるのです。
幽霊も、人の心の表れでしょうか。離れていても娘の心を捉えて放さない母という存在の威力。
 秋田の森の小さな池で、トンボが産卵中でした。
秋田の森の小さな池で、トンボが産卵中でした。
近づくことができなかったので、荒い画像になりました。
トンボが飛んでいると、吸血昆虫が寄ってこないので、
安心して、山歩き森歩きを楽しめます。
虫除けスプレーより、トンボの存在の方が、楽しい感じがします。
それがオニヤンマなら、もはや向かうところ敵なし。
トンボの産卵を見たのは初めてでしたが、ずいぶん時間をかけていました。
いっぱい産むのでしょうか。それとも難産だったのでしょうか。
この夏最後の休日。我々の他に、人間は一人もいなかった。
 「まさかそんな愚かなことをするはずがない」
「まさかそんな愚かなことをするはずがない」
そういう予測を裏切って、戦争が起こる。
予測を裏切って、風向きが変わる。
昆虫や植物には優れた生存戦略があるようだ。
先日、ロシアの永久凍土から、新種の線虫が発見され、
それが4万6000年の休眠から目覚め、動き出したという報道(2023年8月8日)。
温暖化の中で溶け始める永久凍土から出てくるものは、線虫だけではないはずだ。
新種のウィルス、微生物、彼らも持っている休眠という戦略。 この戦略は素晴らしいけれど、空恐ろしい。

すっかり大きくなり、口も閉まっています。
巣立ち前の最後の写真。
面構え、三羽三様。
つぶらな瞳だが、厳しい表情だ。
小さな頭でも、驚異の脳力で、生き抜くのだね。
<巣立ち>ました。
 職場の建物の一角に、毎年ツバメが巣をかけるのだそうで、
職場の建物の一角に、毎年ツバメが巣をかけるのだそうで、
7月3日、夫がそれを撮影しました。
食いしん坊の三羽のツバメの子。
あっという間に大きくなって、もうすぐ巣立ちのようです。
生存競争は、厳しいものだと思います。
厳しいからこそ、早く成長する。
それぞれにそれぞれの一生があって、
精一杯生きているのだと思う。
みんながんばってね。
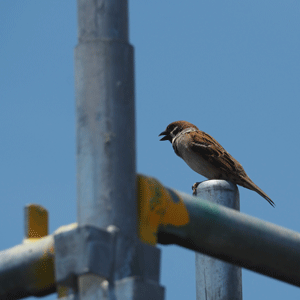 マンションの大規模修繕。
マンションの大規模修繕。
足場が組まれた直後は、近所の鳥たちが大騒ぎだった。
そのうち、この足場がすっかり気に入ったらしく、
朝方など、よく遊びに来ていた。
足場の雀が、歌っている。
天網恢々疎にして漏らさず <テンモウカイカイソニシテモラサズ>
「天に張り巡らされた網は、ゆったり大きく私たちを包み、
その目は粗いけれど、悪は必ず捕らわれる」
足場に囲まれながら、そんなことを考えている時、
善き職人さん達は、黙々と働いてくれていたのである。
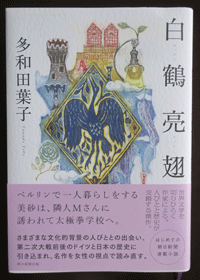 多和田葉子さんの小説「白鶴亮翅」(ハッカクリョウシ)。
多和田葉子さんの小説「白鶴亮翅」(ハッカクリョウシ)。
主人公の名前が「高津目美砂」で、偶然私と同じ、砂の美砂。
高津目美砂さんは、ベルリンで一人暮らしをする翻訳家で、
この美砂さんを通じて、共にひとときベルリンに暮らし、
国籍からも感情からも少し自由な「その人」の世界で、
さまざまな文化・歴史・物語・傷や躓きについて考えることになります。
幽霊ともすれ違うことになります。
言葉にできなかったモヤモヤしたものが、言語化されていく感覚もあり、
いろいろな場面で、腑に落ちるものがありました。
現在進行形の世界で、ニュースは、ロシア・ウクライナのダムの決壊を伝えています。
それは遠いどこかの誰かのことではないと感じています。
国境などどうでもいいから、私たちの日常をこれ以上壊さないで、と叫びたくなる。